食中毒の原因は何?
細菌もウイルスも目には見えない小さなものです。細菌は温度や湿度などの条件がそろうと食べ物の中で増殖し、その食べ物を食べることにより食中毒を引き起こします。一方、ウイルスは、細菌のように食べ物の中では増殖しませんが、食べ物を通じて体内に入ると、人の腸管内で増殖し、食中毒を引き起こします。また、ウイルスは低温や乾燥した環境中で長く生存します。
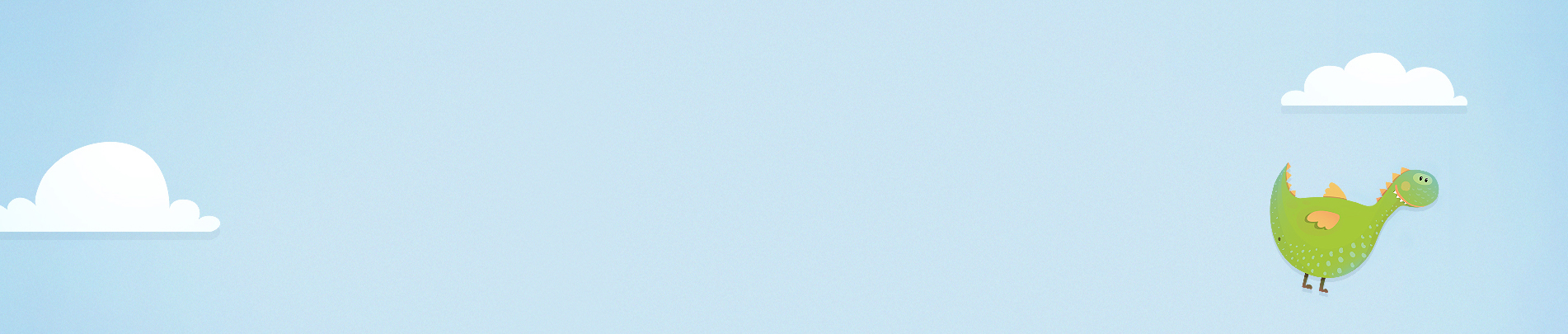
細菌もウイルスも目には見えない小さなものです。細菌は温度や湿度などの条件がそろうと食べ物の中で増殖し、その食べ物を食べることにより食中毒を引き起こします。一方、ウイルスは、細菌のように食べ物の中では増殖しませんが、食べ物を通じて体内に入ると、人の腸管内で増殖し、食中毒を引き起こします。また、ウイルスは低温や乾燥した環境中で長く生存します。
健康サポート薬局は、地域の皆さんの健康の維持・増進を積極的に支援する薬局です。薬に関することに加えて、健康に関わる様々な相談に乗ってもらえます(健康サポート薬局は、平成28年(2016年)10月から始まった制度です)。
また、令和3年(2021年)8月からは、病気になった患者が安心して薬による治療が受けられるよう、地域の医療・介護の関係施設と連携しながら患者を支えていく役割を持つ薬局(「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」)を認定する制度が始まりました。
毎年秋から冬にかけては、インフルエンザの流行シーズンです。高熱や関節の痛みなどを伴い、人によっては重症化するおそれもあります。流行を防ぐためには、原因となるウイルスを体内に侵入させないことや周囲にうつさないようにすることが重要です。インフルエンザの感染を広げないために、一人ひとりが 「かからない」「うつさない」対策を実践しましょう。
必要のない抗菌薬を服用することで、体内にいる細菌がその抗菌薬への耐性を持つ可能性が高くなります。また、処方された抗菌薬の服用を自分の判断で途中で止めるなど、指示された服用方法を変更してしまうと、残った細菌から耐性菌が出現する可能性が高くなります。こうして生まれた耐性菌が、自分の体内にとどまり(保菌)、また周囲の人々に伝播していくことで、薬剤耐性は広がっていきます。そして、抗菌薬の効かない細菌が広まることで、感染症に対する有効な治療法がなくなってしまうのです。
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気やけがなどで障害が生じたときには、「障害年金」が支給されるのをご存じですか。障害年金は、眼や耳、手足などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場合なども支給の対象になります。
119番通報で駆け付けた救急隊員は、傷病者の受診歴や薬剤情報などを基に、搬送先医療機関の選定や、救急車内での処置を行います。ところが、本人が意識を失い家族が動揺していたり、意識があっても処方された薬の名前を思い出せなかったりする場合、救急隊員の情報把握が難しいことがあります。こうした「もしも」のときに役立つのが、マイナ保険証を活用した「マイナ救急」です。ここでは、その取組やメリット、利用方法について分かりやすくご紹介します。
健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関・薬局でご利用できます。
スマートフォンのマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用いただけます。※スマートフォンのマイナ保険証が利用できる施設か事前にご確認ください。※スマートフォンへのマイナンバーカードの追加は任意です。
食事を作ったり、選んだりするときに、主食、主菜、副菜を組み合わせ、栄養バランスのとれた食事を意識しましょう。栄養バランスのよい食習慣の人は、そうでない人と比較して死亡のリスクが低くなることが報告されています。
日本では国民の2人に1人が"がん"になり、4人に1人が"がん"で亡くなっています。がんにかかる可能性(罹患率:りかんりつ)は年齢とともに高まりますが、特に働き盛りの女性では、同世代における男性の罹患率を大きく上回っています。...
日本人の死因の約5割は、がんや心臓病、脳卒中などの生活習慣病です。生活習慣病の予防と早期発見・治療に重要なのが、「特定健診(いわゆるメタボ健診)・特定保健指導」や「がん検診」などの定期的な受診です。健診(検診)の重要性とその内容、そしてふだんの生活での心がけなどをご紹介します。
「健康寿命」とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことです。世界保健機関(WHO)でも新たな指標として導入されています。
従来の指標であった「平均寿命」には、寝たきりや認知症などを患って介護が必要となる期間も含まれていました。我が国の平均寿命は世界有数の長さである一方、健康寿命との差(つまり、健康上の問題で日常生活に制限のある生活をする期間)は、男性が8.73年、女性が12.06年と決して短くありません。